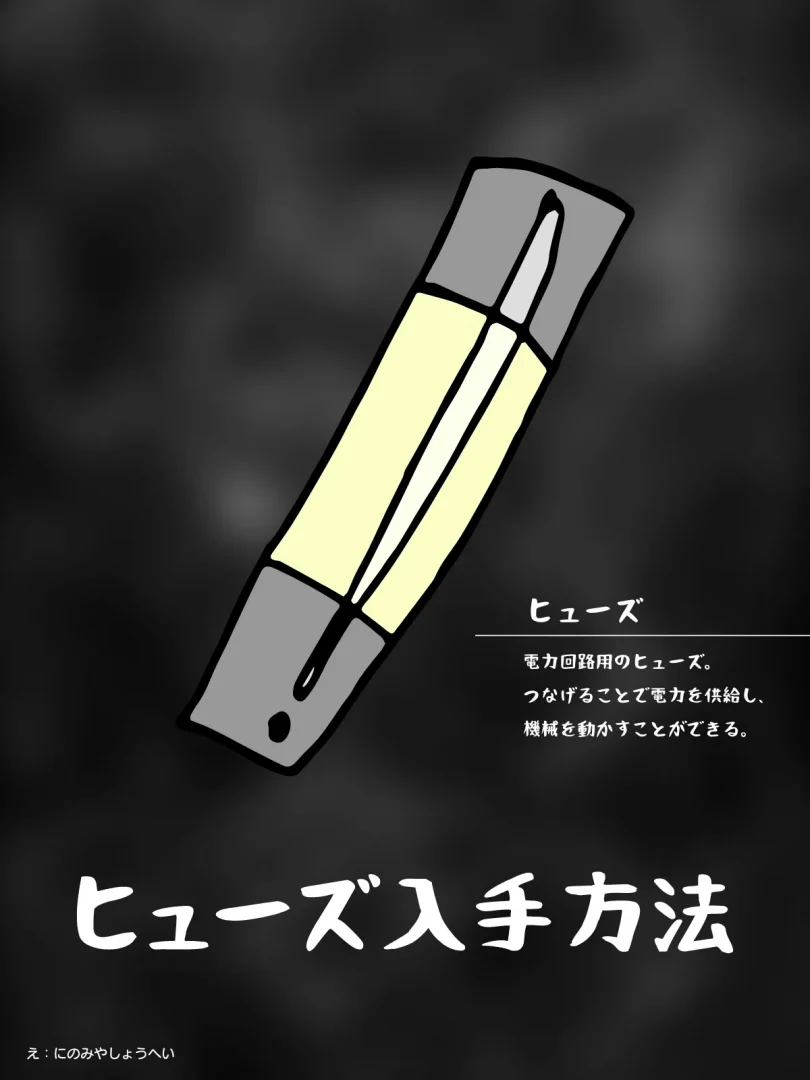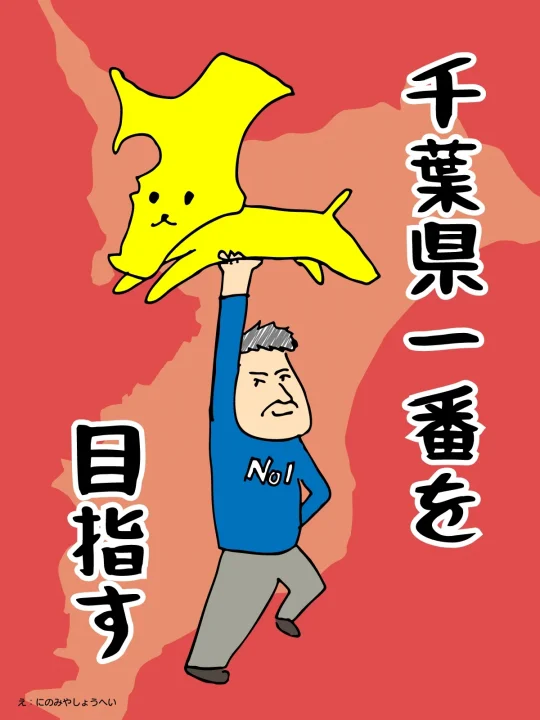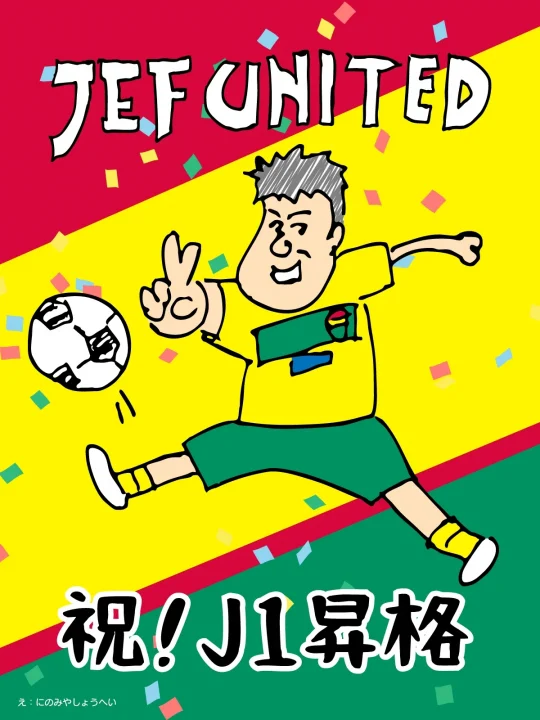伝えるには「ビジュアル化」と「技術」が欠かせない
どう説明していくかって、表現力とか技術がないと人に伝えるのは難しいですよね
「みんなが良くなるといいな」「ハッピーになるといいな」っていう気持ちでスタートしても、その想いが届かないこともあります。だからこそ、ビジュアル化しセンスよく伝えてもらうことがすごく大事なんです。日常的に何か企画を進めるときは必ずビジュアル化してから進めたい。みんなが方向性を間違えないし、思いつきで動くこともない。
結局のところ「伝える技術」って大事なんです。アウトプットの仕方ひとつで、いいものも悪いものも全然違って見える。だから、リクライブの皆さんにお願いしているのは正解だったなと思います。
電気の話を、ちゃんとしよう
リスナーさんから「タイトルコール、もっと“猪木っぽく”やってください!」ってタイトルコールやコーナーについてアドバイスをもらったんです。それを聞いて「あれ、そういえば電気の話してなかったな」と気づいたんですよね。
ビリビリでんきショックって名前なのに、初回くらいしかしていなくて。だからたまには、電気の豆知識じゃないですが、安全性と便利さと危険性を少し伝えられたらなと思います。
最近のニュースも含めてなんですが、問い合わせの上位が「ヒューズが飛ぶ」という相談なんです。これ、意外と知らない方が多いんですよ「電気が急につかなくなった」「リビングはつくのに和室だけつかない」「トイレは使えるけど電子レンジが動かない」そんな症状のとき、実は“ヒューズ”が原因のことが多いんです。
半分だけ電気が消える理由
「リビングはつくのに和室だけつかない」「トイレは使えるけど電子レンジが動かない」には、ちゃんと原因があるんです。
外から家に引き込まれている電線は、一般的に3本あります。単相三線式と言うんですが、赤・白・黒の3本で構成されてるんです。赤と白の間で100V、白と黒でも100V、赤と黒の間では200Vが取れるようになってます。なので、もし赤の線につながっているヒューズが切れたら、白と黒の線だけ使える状態になるんです。
結果として、リビングは使えるけど和室やトイレは使えない、みたいな“家の半分が暗い”状態になる。 これが「ヒューズが飛ぶ」っていう現象なんですよ。
ブレーカーと分電盤の関係
ブレーカーと分電盤の違いも聞かれます。分電盤っていうのは、ブレーカーを収めている箱のことなんです。多くは洗面所やキッチンの近くに設置されています。
中を開けると、メインの大きなブレーカーと、小さいブレーカーが並んでいます。大きいほうが全体の電気を管理していて、小さいほうはリビングとかエアコンとか、場所ごとに分かれた回路を管理しています。安全装置の役割を持っていて、電気を使いすぎたりショートしたりすると自動で落ちる仕組みです。
20アンペアが一般的で、それを超えると危険なのでブレーカーがパチンと落ちます。昔は手動で戻してましたけど、今は外のメーターと一体化していて、自動で復旧する仕組みになってるんです。
ヒューズはどこにある?
そもそもヒューズってどこにあるか知っていますか。実は、家の外壁のあたりなんですよ。
電柱から引き込まれた線がメーターを通って分電盤に入るんですが、その途中に電力会社とお客様側の「責任の分界点」があって、そこにヒューズがついているんです。昔のタイプだと劣化して切れやすく、一本だけパチンと飛ぶと家の半分が使えなくなるです
「なんか電気が半分しかつかないんです」と連絡をもらうと、もう大体わかります「あ、それはヒューズですね」と。電話口でお話ししても、だいたい五分もすれば原因が見えてくるんです。
困っている人を放っておけない、電気屋の性
電話では「ブレーカーは落ちてないんですけど」っていうケースもあります。そうなると、電力会社の区分で、電力会社の緊急対応部署に連絡してもらうと無償でヒューズを取り替えてくれるんです。
私たちにとっては1円にもならない対応なんですが(笑)でも困っている方がいれば放っておけません。ただ、電話口でボリュームのある説明をするんですよ「分電盤ってどこにありますか?」から始まる方も多くて「そんなのうちにないですよ」って言われることもあります。
深夜の電話と「責任施工」
昔は電話回線が1本で留守電を入れない時代があったんです。そうすると「電気がつかないんですけど」って夜中に電話が鳴るんです。
自宅兼事務所だったので、会長夫婦が普通に取っちゃうんですよ。そして「どうしたらいいんだろう」と私に電話が来る。夜中に出向いて仮で電気をつないだり、「どこの回路を優先したいですか?」と聞きながら応急処置をしたこともあります。そのときはさすがに費用はいただきましたけど、基本的にこういう対応は“責任施工”の範囲でやることが多いんです。
住宅の分電盤には「施工した電気工事会社のラベル」が貼ってあることが多くて、電話番号も書いてあります。だから、たとえ10年、20年経っててもトラブルがあったとき電話がかかってくるんです。
夜間対応の難しさと課題
実は10年も経つと、もう保証の範囲外なんです。家を建てた工務店の連絡先がわからないこともあるし、会社自体がなくなっていることもある。だから結果的に、うちに電話が来るんですけど。
でも、社員は昼間は現場に出ているので、夜の緊急対応まではなかなか難しいんです。水道だと「クラシアン」みたいな業者さんがあるじゃないですか。あれと同じで、電気にも「緊急ダイヤル」があるんですよね。
実際にエネオスさんとかが24時間の電気トラブル窓口をやっていて、出張作業もしてくれるらしいんです。そういうところにお願いするのがいいんですけどね。
ネット検索での“千葉電気工事問題”
ちょっと余談ですけど、「千葉電気工事」で検索すると、千葉さんがやっている電気工事会社の次くらいに出てくるんですよ。
昔はSEO対策もしてたので、うちの会社も上位に出てたんです。岩見沢にある「千葉さんの電気工事会社」が1位で、その次が「千葉電気工事」という会社、で3位にうちが出てくる感じでした。だから、ホームページにも「お困りのときはこちら」と問い合わせ先を載せてるんです。でもやっぱり、困ってる方はとりあえず電話してきますよね。
電気のある暮らしを守る
こうして話していると、ほんと久しぶりに“電気の話”をしているなと思いました
「ビリビリでんきショック」って名前の通り、最初のコンセプトは“電気のことを語る番組”だったんです。
33回目にしてようやく初心に戻れましたね(笑)こういう“暮らしの電気のお困りごとコーナー”を、今後も少しずつ取り上げていきたいですね。知らないことって、まだまだいっぱいありますから。私自身、電気屋になる前は分電盤がどこにあるかすら気にしてませんでした。また別の機会に詳しくお話したいですね。
では今週も電気に関してもご安全に!
話し手
勝谷 篤史
株式会社岡田電気工事代表取締役
義父が経営する岡田電気工事の事業承継のタイミングで業界未経験ながらも転身。現在は同社の代表取締役として皆様のお力を借りなからなんとかやっています。