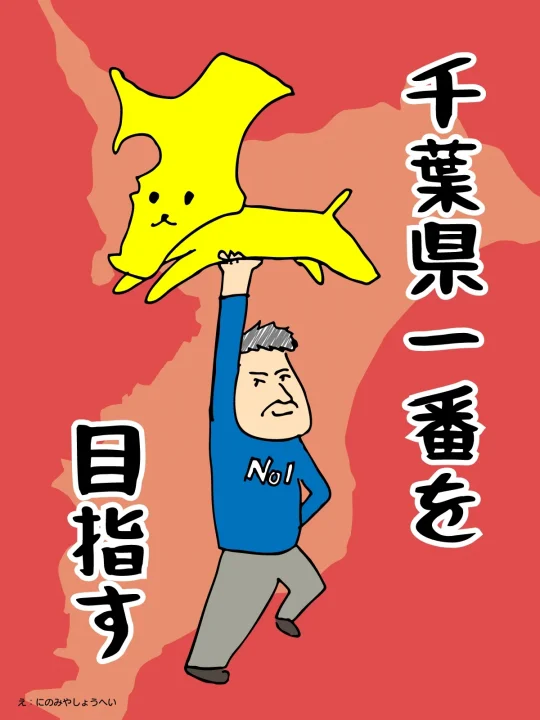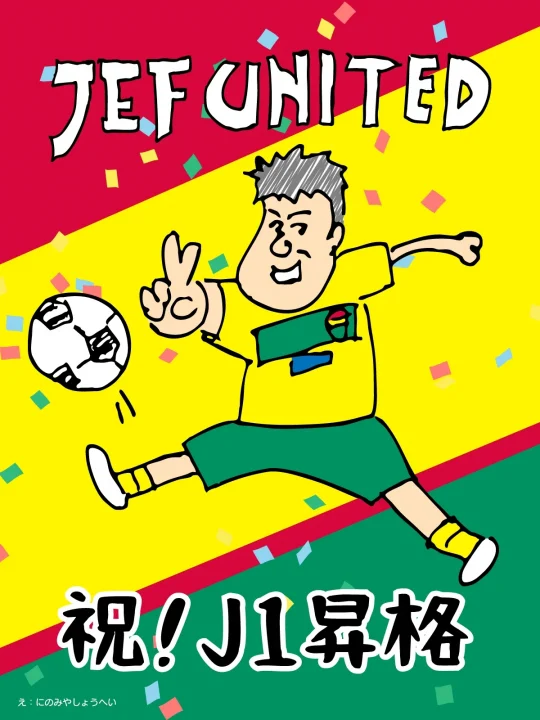突然の訃報
今日は少ししめっぽい話からになります。長年お世話になってきた建設会社の社長さんが、急に亡くなられました。
私と同じ48歳。同世代ということもあって、本当に驚きました。
病気の話も聞いたことがなく、元気な印象しかなかったので「くも膜下出血」という知らせにはただただショックでした。
同い年の仲間が亡くなるという現実
これまでも同級生が亡くなったという話は耳にしたことがあります。20代の頃に一人、30代の頃に一人。ただ、そのときはまだ先のことのように感じていました。
けれど今回は違いました。現場を共にしてきた、同じ社長という立場の仲間です。
「これからも切磋琢磨していける」と思っていた人が突然いなくなる。
驚きと悲しみが押し寄せ、そのあとには「会社はどうなるのだろう」という現実的な思いも浮かんできました。
経営者として備えておくべきこと
経営者は家庭だけでなく、会社全体の責任を負っています。
もし自分に何かあったとき、残された人が困らないようにしておくことは本当に大事だと思います。
私も私的なものですが、遺書のようなメモを残しています。
「会計はここにお願いしている」「このパスワードはここにある」といった最低限の情報を書き留めているんです。
突然の事故や病気があったとき、残された人が動けるように。経営者だからこそ欠かせない備えだと感じています。
放送事故から学んだこと
ここからは少し話題を変えます。先日「放送事故」という言葉について知る機会がありました。
ラジオの世界では「5秒間の沈黙」が放送事故になるそうなんです。総務省への届け出まで必要だと聞いて、驚きました。
私たちのポッドキャストはもう少し自由で、沈黙や間があっても編集で整えることができます。
ただ、その違いを知ったことで「MCとしての緊張感」というものを改めて感じました。
二人で話すことの強み
地方局のラジオには、一人で長時間番組を回すパーソナリティもいるそうです。
その大変さを思うと、二宮さんと二人で掛け合いながら進められるのは大きな強みだと思います。
聞き手がいて、会話のキャッチボールがあるから沈黙も防げる。
危ない話題になりそうなときも、自然と相手が流れを変えてくれる。
そういう安心感があるから、私は自由に話せるんだと思います。
まとめとこれから
今回は訃報の話から始まりましたが、最後には「放送を続ける意味」を改めて考える時間になりました。
この番組はほとんどカットをしていません。それでも楽しんでいただけているのは、素のままを出しているからだと思います。
これからも放送事故を恐れすぎず、自然体で届けていきたいです。
ぜひ感想やお便りをいただけると嬉しいです。
それでは、みなさん今週もご安全に!